はじめに
最近は、犬を買い始めたらまずワクチンをという飼い主さんがずいぶん増えてきたように思います。しかし初めて子犬を飼う方の中には、ワクチンをいつうてばいいのか、どんなワクチンがあるのかなど、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
ワクチンの種類
犬のワクチンには大きく分けて狂犬病ワクチンと混合ワクチンの2種類があります。
狂犬病ワクチンは狂犬病予防法で生後91日齢以上の犬に年一回の接種が義務づけられています。狂犬病の日本国内での発生は1957年以降ありません。しかし、狂犬病は発生していない国のほうが少ないぐらい、今現在も世界中の国々で人や動物にとって脅威であることを知っておいてください。
混合ワクチンとはその名前の通り、何種類かのワクチンが一本の注射の中に混ざっているワクチンです。まず基本の混合ワクチンである5種混合ワクチンからご説明していきます。5種混合ワクチンとは次の5種類の病気を予防できるワクチンです。
・ 犬ジステンパーウイルス感染症
・ 犬パルボウイルス感染症
・ アデノウイルスⅠ型感染症(犬伝染性肝炎)
・ アデノウイルスⅡ型感染症(犬伝染性気管炎)
・ パラインフルエンザウイルス
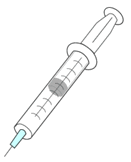
この5種類の感染症は伝染力が強く、また発症した場合の重症度も高いため、どの犬にもワクチンによる予防が必要な病気です。この5種類にコロナウイルス感染症や2?3種類のレプトスピラ感染症のワクチンを追加したものが、6?9種混合ワクチンということになります。コロナウイルスやレプトスピラのワクチンは、必ずしもすべての犬に必要というわけではありません。
ワクチンには残念ながら副作用の問題もあります。熱が出る、顔が腫れるといった一時的なものから、ごくまれにですが全身性ショックなどの命にかかわるようなものもあります。どのワクチンが愛犬に最適かは、犬の年齢や環境によって変わってきます。かかりつけの病院の先生とよく相談してからの接種をお勧めします。
接種の時期
ワクチンは接種をすれば100%病気を防げるわけではありません。体質によってはワクチンを接種しても全く、あるいはわずかしか病気に対する抵抗力がつかない犬もいます。特に生後間もない子犬は移行抗体という母親譲りの免疫が病気の発症を防いでくれますが、ワクチンによる免疫反応も防いでしまいます。移行抗体は子犬の成長とともに減少していき、それにともなって病気に対する抵抗力も減少していきます。移行抗体の消滅時期は犬によって違います。移行抗体のない犬もいれば、12?14週齢ぐらいまで残っている犬もいます。
したがってワクチンは、移行抗体が無いかもしれないことと12?14週齢になるまで残っているかもしれない、という2つのことを想定して、4~5週齢の早いうちに第一回目の接種をし、以降3?4週おきに12?14週齢になるまで複数回接種がする必要があります。
ワクチンを接種してから病気に対する抵抗力がつくには少なくとも2週間はかかります。この間は屋外や犬の集まるところに連れ出すのは控えたほうがいいでしょう。なおワクチンによって接種できる年齢や初年度の最終接種時期は異なります。愛犬のワクチン接種プログラムで疑問があれば遠慮なくかかりつけの先生に聞いてみましょう。次年度からは一年に一回の接種が、獲得した免疫を維持するのに望ましいと言われています。
接種時の注意点
ワクチンを接種する際に注意すべきことがいくつかあります。まず犬を飼い始めてから7?10日間ぐらいは家でよく観察する必要があります。食欲はあるか、元気はあるか、下痢や嘔吐はないか。環境の急激な変化で体調を崩すことはよくあることです。犬は自分で体調の良し悪しを言うことができません。家での愛犬の様子をしっかり獣医師に伝えられる人が病院に連れて行ってください。
ワクチンを接種したあとは安静に努め、興奮させたり、激しい運動をさせたりしないよう注意してください。できれば一時間ぐらいは病院内か、すぐに病院に行けるところで様子を見ているほうが安全です。非常にまれではありますが、接種後数10分?数時間後にショック状態といって命にかかわる危険な状態になることもあります。できればワクチンは接種後に何かあっても病院ですぐに診てもらえるように、午前中早い時間に接種することをお勧めします。
このようにワクチンはいいことばかりではありませんが、愛犬の健康を守るのにとても効果的であることに変わりありません。愛犬の負担をできるだけ軽くして、かつワクチンのメリットを最大限にいかせるような、接種の仕方を考えてみてください。


